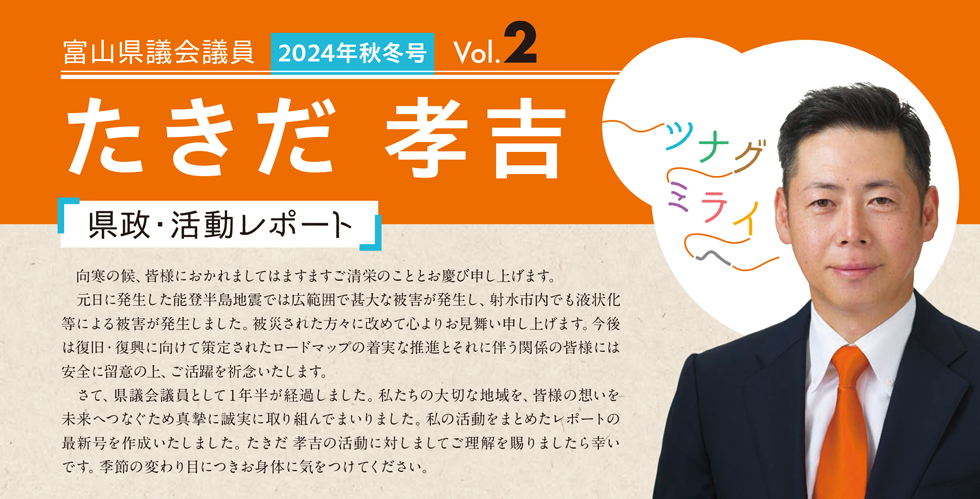2024年度議会活動記録
令和6年2月定例会 一般質問>>一般質問・予算特別委員会での
質問答弁ダイジェスト 全12問
Q.能登半島地震を受け今後の防災意識向上のために動画制作をしてはどうか。
【A】
今回の地震を受け県民の防災への意識、関心は大いに高まっており県民に分かりやすく防災対策を伝える動画を制作し啓発に活用することは、とても有意義な取り組みと考える。
検証作業を進める中で、防災対策を伝える動画制作を今後の対策に盛り込むことを検討するなど、県民の防災意識の向上に向けた取り組みの強化に努める。
Q.県立学校は避難所としての機能強化に向け太陽光発電等の再生可能エネルギー設備の導入を加速してはどうか。
【A】
県カーボンニュートラル戦略では県有施設の50%以上での設置を目標としている。県教委では54施設で設置可能と考えており、その50%27施設での設置を目指している。10施設は導入済みであり、今後17施設において導入に向け取り組んでいく。
Q.復興を見据え石川県と連携し能登半島国定公園を中心とした滞在型エリア観光の推進に取り組んではどうか。
【A】
能登半島国定公園は、長い海岸線を主体として、石川県と富山県にまがる様々な観光地も含んだ魅力的なエリアであり、地震からの復旧状況を注視しながら滞在周遊観光促進に向け石川県やJR、地域交通・観光事業者等と連携して準備を進める
Q.伏木富山港の機能強化およびカーボンニュートラルポート形成に向けた取り組みの進捗状況は。
【A】
地震により、伏木富山港も大きく被災したが港湾機能の早期復旧を図っている。カーボンニュートラルポートの形成に向け、官民が連携する協議会を設置して検討を進めている。今後も脱炭素化など時代の要請に応じた港湾機能の強化を図り、伏木富山港が環日本海・アジアの交流拠点としてさらに発展するように取り組んでいく。
Q. 高志の国文学館は室井滋さんを館長に迎え絵本の魅力紹介にも積極的に取り組んでいるが射水市大島絵本館との連携による絵本文化振興を図ってはどうか。
【A】
これまで企画展やトークイベントを両館で実施したほか、文学館での絵本フォーラムに大島絵本館の副館長にパネリストとして参加いただいた。また大島絵本館の広報誌に室井館長がエッセイを寄稿されるなど、相互の連携を深めている。今後も大島絵本館と共に文化振興につなげていく。
Q.県立大学ではアメリカに新たに研究拠点を設置し国際的な共同研究を推進していくが海外からの学生受け入れを拡充するなど国際化をさらに進めてはどうか。
【A】
令和6年10月からギリシャ共和国クレタ工科大学との間で、環境・社会基盤工学科の学生や大学院生の交換留学を行う予定である。またシリコンバレーオフィスの設置等、海外大学との共同研究の一層の推進と学生のグローバルマインド養成に取り組んでいく。
令和6年6月定例会 予算特別委員会>>一般質問・予算特別委員会での質問答弁ダイジェスト 全14問
Q.献眼、臓器移植及び骨髄移植のドナー登録の拡大や献血者の確保に向け、どのように取り組むのか。
【A】
各関係機関との連携・協力をさらに推進しつつ、ドナー登録には年齢制限があることから特に若年層を重点的にSNS、ポスター、パンフレット等による普及啓発に取り組んでいく。
Q.全国的にDVにおける男性の相談件数が増加しているが、本県のDV被害の状況や男性被害者からの相談状況を踏まえ、男性用シェルターの設置を進めてはどうか。
【A】
県警によると昨年のDV関連相談のうち約25%が男性被害者事案だった。県民共生センターでは平成31年から男性相談員による男性のための相談対応を開始している。来年度はDV基本計画を改定し、その中で男性の被害者への支援、男性用シェルターの必要性について検討していく。
Q.今夏も酷暑が予想されているが、熱中症対策として県有施設をクーリングシェルターとして積極的に開放するよう取り組んではどうか。
【A】
昨年の記録的な豪雨による被害や対応の検証結果などを踏まえ、出水期においてどのような対策を講じるのか。
Q.「ダム等に関する情報提供のあり方検討会」の取りまとめの中から、今年の出水期にはダム等の情報提供の充実に取り組んでいる。和田川ダムでは、利水に影響がない範囲でダムの貯水位をあらかじめ低下させ、治水容量を確保する試行を行っている。また洪水が予測される際、水位をさらに最大60㎝下げ、治水容量を約14%増加できると見込んでいる。
【A】
県外に本校がある広域通信制高校が設置する県内の協力施設に通学する生徒についても、就学支援金の県単独上乗せ分の対象とするよう制度を見直してはどうか。
Q.献眼、臓器移植及び骨髄移植のドナー登録の拡大や献血者の確保に向け、どのように取り組むのか。
【A】
県内の広域通信制高校には、多様な生徒が在籍しており学び直しの機会の提供などの役割を担っていると考えるが、他県が認可主体であるため進学している高校生の実態等が把握できないことから対象外としているが他都道府県での取扱いを十分調査研究するとともに国の責任において、格差是正に向けた措置が講じられるよう県議会とともに、国に対し要望していく。
Q.県の有益な情報をPRするためにHPやSNSなどを用いているが、5つの県公式SNS[
X(旧Twitter)、LINE、Instagram、YouTube、note]について、それぞれの特徴をどのように捉え、高い効果が得られるよう運用しているのか。
【A】
県公式SNSで最もフォロワー数が多いのはXで約5万人。今後も職員チームによる動画制作や画像・映像、長文による施策の裏側紹介等、それぞれの媒体が持つ特徴を最大限に活かして効果が高い情報発信、県民のニーズ把握に取り組んでいく。
活動の記録
バックナンバー